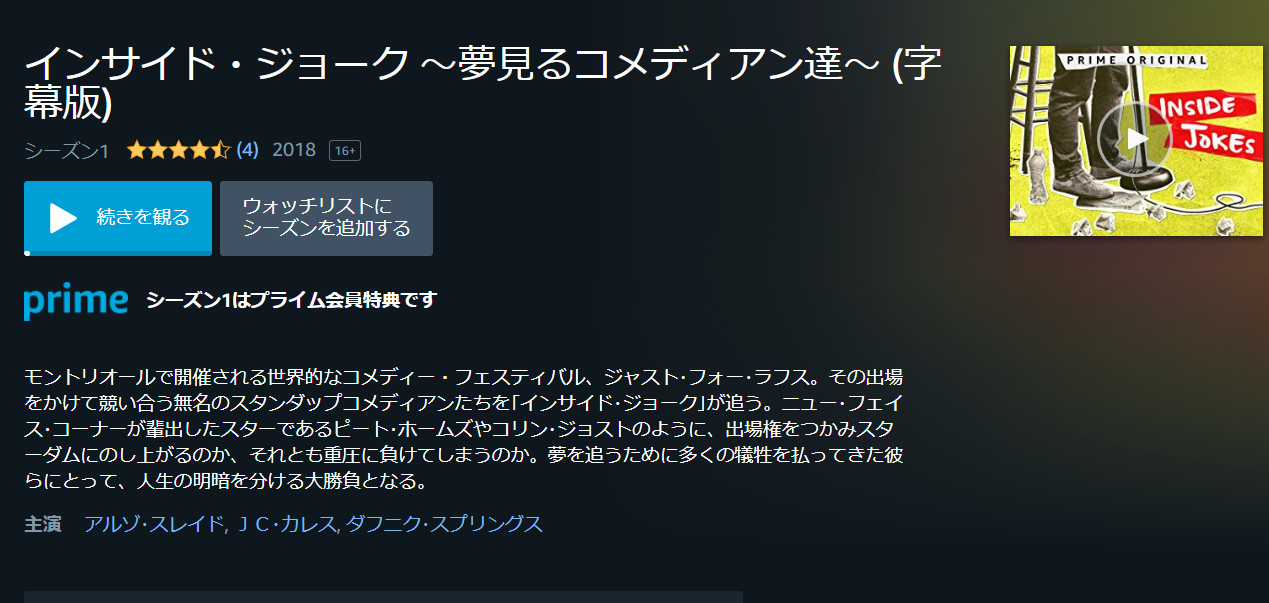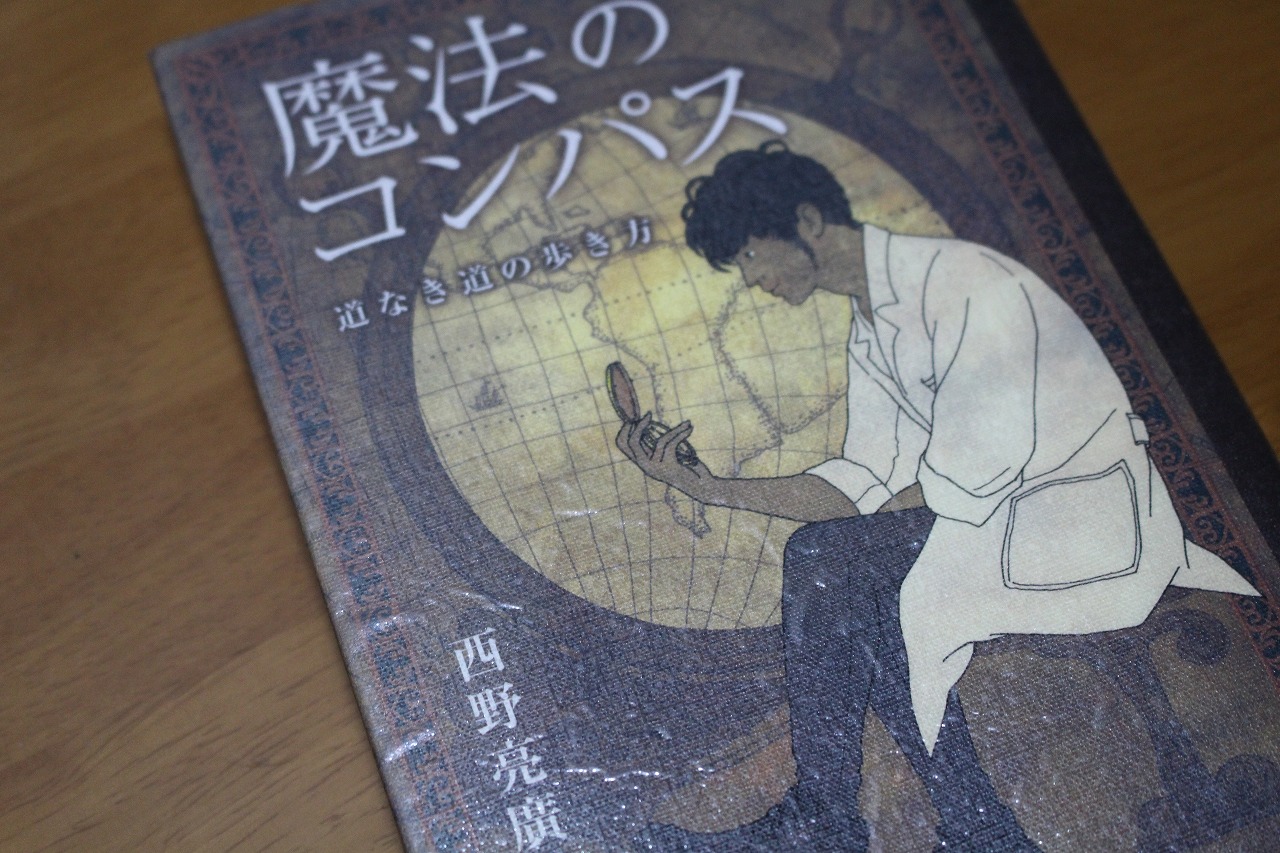お笑いが好きです。気づけばこのブログでは、コメディアンがやっていること(本やポッドキャストなど)についての投稿が多い。今回もまさしくその路線です。Amazon Prime VideoのInside Jokesというドキュメンタリーがおもしろいので、今日はそのことについて書いてみます。
最初にどんなドキュメンタリーかというと、カナダのモントリオールで開かれるJust For Laughsというお笑いイベントの舞台に立ちたい、売れていないコメディアンを追うシリーズです。登場するのは、自らの人生に真っ直ぐに生きている7人のコメディアンたち。化学の学位を持っていてその道に就職できたけどしなかった人、かつてはワシントンD.C.で政治の仕事をしていた人、子どもがいて年間50週は外で巡業活動をしている人、昼間は家具店で働いて夜はコメディアンとして活動する人などなど…。アメリカのロサンゼルスと、ニューヨークで活動する7人たちのコメディアンを追っていきます。
シリーズは全6回で、追っている7人全員が本選に進めるわけではありません。選ばれる人、選ばれない人、それぞれの活動を追っていきます。ドキュメンタリーでは、自分たちでジョークを披露する場所を作ったり、そのためにチラシを配ってまわったりしている姿も映し出されています。その姿を見ると「ああ、この人たちは本当に無名なんだ」ということがわかってきます。察するに生活はあまり楽そうではない。でも彼らは生活が楽かどうかじゃなくて、自分が信じていることをやることで生きています。
なんでこのシリーズにそんなに惹かれるているのだろうと考えると、思い当たるのは彼らの正直さでした。シリーズでは、コメディアンとして活動している彼らを追うと同時に、私生活も追っていきます。ガンガンにすべっているところも撮られまくっているし、住んでいる家での撮影もあるし、実家の家族も登場します。家族のサポートも描かれているけれど、ある人のお父さんに会おうとするも連絡が来ず泣いてしまう場面や、また別の人の両親にゲイとしての自分をうまく受け入れてもらえず苦しんでいるところや、会って受け入れてもらおうと対話をする様子も撮られています。オーディションに受かれば、カナダについたあとの浮かれている感じの様子も映し出され、でも同時に、今までの何倍ものサイズの客席にひるみ、不安をいっぱい感じている様子や、本番前の張り詰めた空気感も伝わってきます。
とにかく、喜び、悲しみ、不安、コメディにかける覚悟や、自分の感情がまとまらずごにゃごにゃっとした感じなど、人らしい感情がまるっと映像から伝わってくるのです。個性豊かで、みんなそれぞれの方向からコメディにはまっすぐで、正直です。人らしい感じと、まっすぐに目的めがけて進んでいく感じが見てて、心地よいです。
多くの感情が感じる環境は違っても理解ができることで、共感できると思います。国籍は違っても、感じることは一緒なんだなあということをしみじみと感じるドキュメンタリーじゃないかなあと思います。
私はこの人たちのように、まっすぐに生きていない、意志を持てていない、捨て身で挑めていない…。彼らの覚悟、意志が伝わってくる言葉を聞くたびに、こんな感じのことを思っていた気がします。一番最初に見てからしばらく経っていますが、節目節目に思い出してしまうドキュメンタリーです。
おもしろいのでぜひ見てみてほしいです!