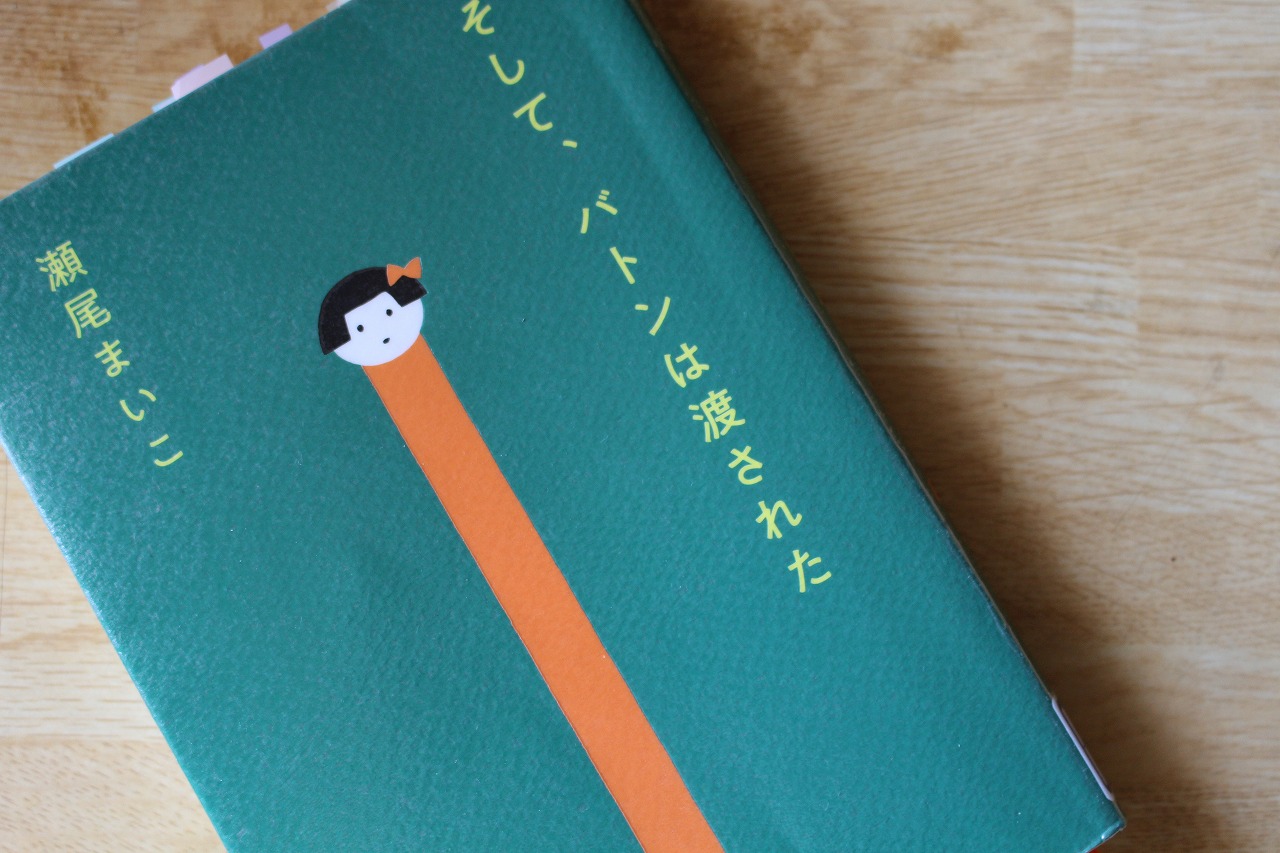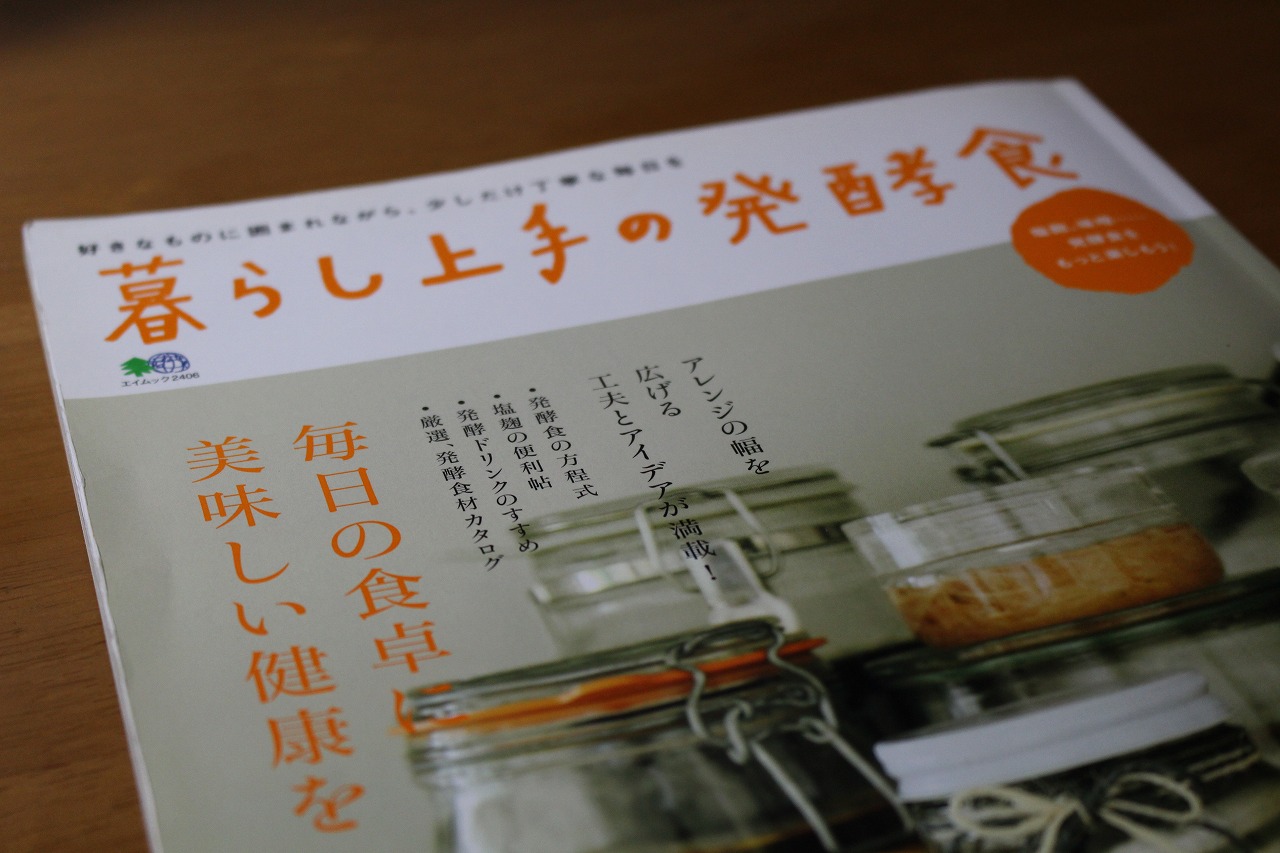本や映画を見たとき、突き動かされるものがないと感想って書けないものだな、と最近思います。
数日前に読み終わった「そして、バトンは渡された」を読んでいるときは、読みながら泣いたり笑ったり、何度も気持ちを揺さぶられました。そこで、今日は感想を書いてみます。
まず、本のあらすじは、Amazonから引用させてもらいます。
森宮優子、十七歳。継父継母が変われば名字も変わる。だけどいつでも両親を愛し、愛されていた。この著者にしか描けない優しい物語。 「私には父親が三人、母親が二人いる。 家族の形態は、十七年間で七回も変わった。 でも、全然不幸ではないのだ。」 身近な人が愛おしくなる、著者会心の感動作
何気ない生活のなかにある、大切な日常
本には、かなしい描写もありました。でも、本を振り返ると思い出すのは、主人公の優子と、3番目のお父さんの森宮さんが食事をしている描写ばかりでした。
かなしい描写もあったのに、どうして日常的な光景ばかりが頭に残っているのだろう? 読んだあと、疑問になりました。浮かんできた答えは、登場する親たちの愛情が物語にあふれているからではないか、ということでした。
月末に金欠になってしまう親、交わす言葉は少ない親、高校3年の始業式の朝にかつ丼を出す親。物語には、全然違うタイプの血のつながっていない親が登場します。でも、そのなかで共通するのは、それぞれの親たちが優子を大切に育てているということ。それは行動に現れていたり、行動からうかがうことができたり、食卓に現れていたり…。厚くしっかりとして揺るぎがない親たちの愛情が、物語の根底に丁寧に描かれています。
でも、愛情は与えてくれる人がいても、与えられた方が愛情に応えなければ一方通行になってしまいます。なんでこの物語をあたたかく感じたのかは、異なる親の愛情を優子が受け入れていく様子が、気持ちや行動で表されているからではないかと感じました。親も子もそれぞれ、いろんな思いを抱えながらも、丁寧に、大切にお互いに接する。そのしっかり重なった思いが、かなしさではなくあたたかさを思い出させてくれた気がします。
そして、そのことを象徴する情景の一つが食事のように感じられました。物語の中心に据えられているのは、食の描写。すべての親との関係性が食を通じて築かれていたわけではないですが、「食」での情景が家族のカタチ、姿みたいなものを多く語っています。
そのなかでも際立っていたのが、最後のお父さんである森宮さんと優子が食卓を囲む時間。始業式の朝のかつ丼を出したのはこの人で、週のど真ん中の夕食には餃子も出てきます。でも、森宮さんの思いがしっかりとこもったご飯です。そういうごはんを作ってくれる人がいて、その食事を一緒に食べ、会話もしながら時間を共有し、時間を積み重ねることで優子の日常は過ぎていきます。その日常は、泣けたり笑えたり、みんなどこかあたたかい話ばかりでした。
本のなかで一番印象に残っている言葉は、優子のこんな心の思いでした。
塞いでいるときも元気なときも、ごはんを作ってくれる人がいる。それは、どんな献立よりも力を与えてくれることかもしれない。
私がこの言葉を読んで思い出したのは、近所に住む祖母が台所で料理をしている姿でした。祖母は毎朝5時に家族にお弁当を作り、朝ごはんと夜ご飯も自分の作ったものを食卓に並べます。何十年もその生活を続けています。料理をすることは、きっと彼女にとって馴染んだ生活の一部で、祖母の料理を受け取る家族にとっても、祖母の料理が生活の一部として馴染んでいるでしょう。でも視点を変え、もっとひいて客観的にそのことを考えてみると、毎日コンコンコンと、台所で料理を作ってくれるその日常自体、その祖母の姿自体がありがたく貴重だということに気づきます。
本を読んで感じたことに名前をつけるとしたら、「何気ない日々のなかにある、大切な日常」でした。食事を家族とともにする時間や、食事を作ってもらう時間は、いつの間にか生活の一部として当たり前になっていきます。でも、そうやって受け入れている時間や環境、そうやって積み上げている時間のなかにこそ、本当に大切なものが詰まっているのかもしれない。本を読んで、そんなことを感じました。
物語の食に関する描写は、物語をカラフルに彩っていたなあと思います。よくジブリ映画に出てくる食べ物がおいしそうだというけれど、この物語も引けをとらなかったです。本の中に出てくる料理の細かい描写、優子の料理に対する食欲をそそる感想。どれもおいしそうで、「この材料、配合で作るとおいしいそうだ」と思う料理ばかりでした。
小説に何を求めるか、人によって違うと思います。私は比較的、物語に展開を求めるタイプです。その意味では、この小説は淡々と日常が描かれ、読む手が止まることもありました。ただ、読んでいくと心のすき間をふんわり埋めてくれる物語性があって、読めてよかったなあと感じる1冊でした。気持ちのバランスをうまく保てないとき、なんだか調子が悪いなあと思うときに、優子の言葉や、歴代の親たちのあたたかさあふれる描写を読み返したくなる気がします。
ふんわりとあたたかく胸に響いてくる物語を読みたいとき、この小説はピッタリかもしれません。よかったら読んでみてください。